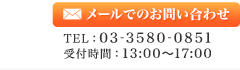(目魁影老の徒然道草 その1)入江一子さん100歳の画家です
入江一子さんは、1916年5月生まれ、先祖は萩の毛利藩の藩士です。今でも毎日、絵筆をとり色彩を極める道を歩み続けています。
昨年2015年7月15日にお会いしました。
梅雨の谷間、青空の広がるとても暑い日でした。午後2時~4時まで、杉並区阿佐ヶ谷にあるシルクロード記念館で「至福の語らい」のひと時を過ごして参りました。地域に密着した美術館(週末のみ開館、500円)である。
一子さんは朝鮮の大邱(テグ)に生まれ、「物心つくころから絵を描くのが非常に好きで、小学校1年生のころには毎日学校が終わると校庭でスケッチをしていました。6年生のときには私の静物画が昭和の御大典で天皇陛下に奉納されました」
17歳の時に女子美術専門学校師範学科西洋画部に入学するために、初めて日本の地を踏んだ。「日本は緑が多いのにびっくりしました。まるで箱庭のようでした」「私は父親の仕事の関係で大邱で育ちました。その影響でしょうか、大陸の土の匂い、荒野に咲く花々、市場の雑踏や聞こえてくる民族楽器の調べにとても郷愁を感じるのです」「私は満州の赤い夕日に感激し、色感のひときわ強いシルクロードの旅を続けてきたわけです。写生旅行を始めるきっかけは日中国交回復の6年後の1978年に日中友好美術家訪問団の一人として北京や雲崗石窟を見て回ったことです。翌年には敦煌の石窟の壁画を懐中電灯で照らしながら写生しました」
「絵を描く基本として、一般的には、まず素描を基にして絵を描きますが、私は素描することより物を描写するとき、描く対象を目にしたとき、色彩の占める割合が圧倒的に大きいと思います。先ず色彩に心を奪われ、描く意欲が起こるということではないでしょうか」「シルクロードを写生旅行すると、太陽の光が素晴らしい。川面は真っ赤に染まる。日本の太陽とは全然違う。衣装も色が素晴らしい。色彩にあこがれる」
40年間にわたる30カ国もの写生旅行で集めて来たパステルや水彩で描いたスケッチと、録音機に残る砂漠の風やシルクロードの街並みのざわめきをアトリエで聴きながら、あふれ出るモチーフを200号もの大作に描き、残すことに挑む。「今が一番絵が分かる」「今が一番幸せ」まるで少女のように瞳を輝かせながら。
目も耳も言葉も何の不自由も無く、一人で自活し、ホームヘルパーに世話になるが、食事も作る。7歳の時に肺炎で死ぬほどの大病をしたが、それからは病気にかかったことはない。何よりも驚かされるのは、明晰な頭脳である。一枚一枚の絵をいつどこで写生したかを克明に記憶しており、絨毯や人形までも入手した時のことを話される。
足も元気で、さすがに5年前からは車輪の付いたシルバーカーを使って歩くそうですが、2時間にわたり、入江一子さんは、淀むことなく生涯99年の想い出、中国から西の果てのモロッコ、南のイエメンまで続けた写生旅行のことなどを、話して下さった。お茶と和菓子を頂きながら、妙齢の御婦人の夢物語を奏でるような、筆舌に尽くせないおもてなしの時間でした。