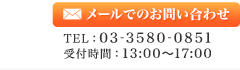(徒然道草その43)現世の「竜宮城」オマーン訪問記③
カブース国王は、父親時代の大臣をすべて罷免した。改革を進めるための人材は全く不足していた。首相の適任者はたった一人しかいなかった。それは兄に反発してドイツに移り住んでいた叔父ターリク・ビン・タイムールであった。それまでお互いに会ったこともない二人であったが、協力して新しい政府機関の創設に乗り出した。しかし人材不足はいかんともしがたく、カブース国王は、外務大臣、国防大臣、石油大臣、財政大臣を兼務せざるを得なかった。
カブース国王は内戦の危機を乗り越えると、内政に全力を挙げて取り組むことになったが、最も重要なことは、経済的な成果を上げ、人々の生活を改善することで、国民の心をとらえ、改革への信頼を獲得することであった。理想主義を掲げて、いきなり西欧的な政治的自由を与えることは、国内の混乱や反発を招き、王政が倒されたり、民主主義を謳いながらも独裁政権が生まれてしまう恐れがあった。何よりも国民の融和を失わないためには、オマーン社会に深く根付いてきた部族社会の伝統文化や宗教を大切にして改革を進める必要がある。カブース国王は、それができるのは議会制民主主義の性急な導入ではなく、王政を守ることだという信念を持っていた。
「他人の手で作られた完成品よりも、自分の手で作った未完成品の方が良い」と慎重にオマーン改革を進めた。
カブース国王の呼びかけに応じて海外にいるオマーン人は続々帰国して若き国王を助けた。マスカットに住む家の無い彼らは、海岸にテントを建てて暮らしながら国家のために働いた。この国は、何もかもがほとんどゼロの状態であった。学校を増やし、病院を建て、国民の生活を守り、向上させることにまず集中的に取り組んだ。どの部族にも教育や医療が分け隔てなく行き渡るように、常に公平を心掛け、国民の不満や混乱が起こらないように細心の注意を払った。文盲をなくし、乳児の死亡率を劇的に改善することに成功した。
行政組織や生活インフラを整えることも急務であった。イギリスはクーデター後のオマーンを新国家としていち早く承認し、改革当初はイギリス人の顧問団が人材不足を補って支援してくれた。カブース国王は、海外から帰国した若者が経験を積み、行政能力を身に着けるのを待って、少しずつ彼らを要職に引き上げていった。初等教育の整備が進むと、さらに高等教育の充実を図り、1986年にはスルタン・カブース大学をマスカット郊外に開校するまでに漕ぎつけた。海外にも多くの若者を留学させた。今では、改革当初から国王を支えた人々も高齢になり、若い人材に国政の担い手を世代交代することを進めている。
カブース国王はターリク・ビン・タイムール退任後には首相も兼務し、現在でも、石油大臣を除く、主要4大臣の兼務は続いている。それは国王専制でも国王独裁でもない。国政の実務は各省次官などの行政トップに委ねながらも、国王がすべての義務と責任を一手に引き受けるという固い決意の証である。
★ ★
立法権のある国会や議会の開設は認めていないが、カブース国王は1981年には国家諮問評議会を創設して、県の代表17人、国家の職員17人、民間の代表11人を選び、国家の開発計画が効率的進んでいるかどうか、国内を巡回して知事や部族の代表に会って意見交換する組織を立ち上げた。3年後に行われた選挙では、議員数は80人に増え、初めて女性2名が選ばれた。
オマーンには憲法は無い。その代わりとして、在位25周年の記念日を前に、
1996年に発令された国王令第101号で国家基本法を発効させた。この基本法に基づき、国家諮問評議会を二つに分けて、新たに国民の代議制機関の第一院として諮問評議会、第二院として国家評議会が設けられた。国家評議会の議員41名は国王が任命した。大臣、副大臣、大使、軍人、治安担当者、大学教授、マスコミ関係者、そして女性議員も5名選ばれた。
イスラーム教では、男性と女性は役割が違うと教える。女性は家庭の中に閉じこもって、外で働く男性に性的安寧を与え、子孫を産むことが務めであるという文化である。そして、女性は夫と父親以外に肌を見せてはいけない。また女性の髪は、男性にとって誘惑的なものであるからスカーフを被って、他人に見られないようにしなければならない。家にお客を招くときも、男性は男性だけで、女性は女性だけで宴会を開く。男性と女性が一緒になることは無い。
ムハマンドは610年に神の啓示を受け、そこからイスラーム教が興るが、それは日本で言えば聖徳太子の時代である。そのころは、東ローマ帝国とペルシャ帝国の間で長い戦乱が続いていて、双方とも疲弊しきっていた。その間隙を衝いて、いわば軍事組織でもあったイスラーム共同体は、一挙に中東地域を制覇してイスラーム教を広げるとともに、アラブ帝国をつくり上げた。戦闘が続けば兵士は死ぬ。すると女性にとっては結婚する相手がいなくなってしまう。そこでムハマンドは「生活できなくなった寡婦を助けるために、妻を4人まで認めた」ことになっている。その寡婦とは、アラブ人だけではなく、征服されてしまった非アラブ人の側の方が多かっただろう。
テロ組織のIS(イスラーム国)の兵士が若い女性を誘拐するようなことが、古い時代には「しばしば許されていた」のかもしれない。クルアーン(コーラン)に次ぐ聖典であるハーディスには、戦闘で手に入れた「戦利品」に対して兵士は慰安行為をすることが許されるという趣旨の表記がある。イスラーム社会では、戦闘に参加して女性を守るのは男性の役目であり義務であるが、女性自身も異教徒から貞節を守る責任があった。1400年前の厳しい攻防の歴史から生まれたこの伝統が、アラブ文化の背景にあるのではないだろうか。
それに比べ、はるか800年後に、「異教徒は人間ではない。殺せ」と命じたローマ教皇、原住民絶滅を図って女も子供も殺し尽くしたコロンブス、このヨーロッパキリスト教徒たちの方が、はるかに残虐なことをしたことは明白である。極東の島国である日本は、こうした史実と無縁であった。
アラブ社会の伝統文化の遵守を極めて重く見るカブース国王ではあるが、新しい国家づくりには女性の力が欠かせないという立場を打ち出している。そのために、慎重に粘り強く、女性の活用を進めている。そういう点では、頑なな保守主義者ではなく「伝統の破壊者」でもある。国王令によって女性を次官に任命し、その後、大臣にも登用した。空軍、陸軍、警察にも女性が職務についている。今では大学生の半数以上を女性が占めるようになっており、スポーツをする女性も多く、ヨットや海水浴をする女性もいる。
しかし市民生活では、田舎でも都市でも、男性は白いディシューダーと帽子、女性はアヤバと呼ばれる黒ずくめのガウンに覆われた民族衣装を纏う伝統を守っている。この服装では、男性は立ち姿で小用をすることは難しい。そのためトイレは、かつての日本の大小共用便器と同じような、しゃがむ方式である。
オマーンはイスラーム教を国教と定める国であり、スンニ派でも、シーア派でもないイバード派がおよそ4分の3を占めるが、信仰の自由も認められている。外国人労働者の中にはヒンズー教徒もキリスト教徒もいる。