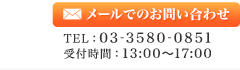(徒然道草その42)現世の「竜宮城」オマーン訪問記②
カブース国王の叡智と献身的なリーダーシップにより、誉れ高き国家に甦った現代のオマーン・スルタン国の姿をこの目で見てみたい――。目魁影老は高ぶる期待に胸を膨らませながら、マスカット国際空港に降り立った。
30歳で国王に就任した、それまで国政に全くタッチしたことのない若き君主は、いかにして部族争いや社会不安を招くことなく、また冷戦時代の共産主義者の挑戦を跳ねのけ、行政組織は無いに等しく、有能な官僚もテクノクラートもいないオマーンを、外国に依存することもなく立て直すことができたのであろうか。国土の80%が砂漠で、農地は僅かに0.3%しかない、ラクダとヤギとナツメヤシだけの最貧のこの地が、世界で最も高潔で、ホスピタリティー溢れる美しい国家に変貌を遂げた秘密はどこにあるのであろうか。
日本に帰国後、レポートをどのように書こうかと迷った挙句に、見たこと聞いたことを反芻しながら、「玉座の改革者」(在日オマーン大使館で頂いた本)を読み直し復習してみた。そしてオマーン改革の成功のカギは、カブース国王の目指した「西欧の議会制民主主義でもなく、共産主義のイデオロギーでもなく、長い歴史の中で根付いたイスラームの教えとこの地の文化の伝統遵守」にあったと確信した。部族や国民の融和を成し遂げることができるのは王政であること、国王はその義務と責任を一手に引き受けなければならないことを覚悟し、あえて父親にとって代わった若き指導者は、妻も子供も家庭もない生活に耐えながら、音楽と乗馬を友とし、改革のために戦い、国民に寄り添い続ける、半世紀にも及ぶ困難な道へと一歩を踏み出した。
★ ★
1970年7月23日、カブース皇太子はクーデターで父親を追放し、国王に就任したことを宣言し、生まれて初めて首都マスカットの王宮に入った。32年間国王を務めた父親は、晩年は鎖国を敷きサラーラに閉じ籠もりきりであったため、マスカットの建物は荒れ果てていた。カブース新国王はすぐにその建物を取り壊し新しい王宮に立て直すことを命じた。鎖国を止め、国民に対するあらゆる規制を廃止、国名をマスカット・オマーンからオマーンに変え、国旗も新しくした。翌1971年には独立を回復し、国連に加盟した。隣接する7首長国はアラブ首長国連邦(UAE)を結成してオマーンには加わらなかった。そのため、ホルムズ海峡に臨むムサンダム半島はオマーンの飛び地となった。石油収入の豊かなカタール、バーレーンはUAEにも加わらずに独立国家の道を選択した。
新しい国づくりに乗り出したオマーンは世界で最も遅れて近代化に着手した国の一つであったから、他国の失敗から学ぶことができた。エジプトやイラクの軍事革命、イラン国王の「白色革命」など、古いものを壊して全く新しい近代的な国家につくり替えるという性急な試みが、次々と挫折する姿を見て来た。若い時のイギリス留学や軍隊経験、幽閉中読んだ歴史書、父親の陥った恐怖からも多くのことを学んだ。
イデオロギーや上からの強制によって国民意識を無理やり変えるようなことをやっては、国民の反発や分裂を招く。新しい国づくりには、国民の同意、社会全体の理解が何よりも必要であり、それは忍耐力と粘り強い努力が無ければできないことである。宗教的、文化的伝統を重んじ、各部族が永年育んできた知恵を生かすことによってのみ、オマーンはかつての栄光を回復できると、カブース国王は考えた。そして部族社会を壊すのではなく、「オマーンの将来の根幹を担うのは部族社会である」と訴え、部族長たちの不安を払拭した。
オマーン第2位の都市サラーラのあるオマーン西部のドファール地域では、1965年に反政府勢力による内戦が勃発していた。中国やキューバが送り込んだ共産主義者たちが、南イエメンから国境を越えて革命運動を起そうとしていた。カブース国王の最初で最大の課題は、この内戦に勝利することであった。ドファールの戦闘はアラビア半島における共産主義拡張の最前線であった。国王自ら作戦の指揮をとって戦ったが戦線は一進一退状態を続け、ヨルダン、イギリス、イランなどの軍事支援を受けて、1975年12月11日にやっと戦争終結を宣言した。
この年はベトナム戦争で米軍が敗れ、エチオピア、アンゴラ、モザンビーク、カンボジア、ラオスで社会主義政権が生まれた、共産主義者にとって輝かしい年であった。